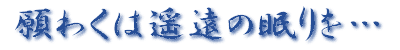
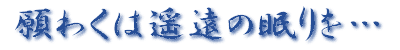
【3】 「ヴォルシェが、行方不明?」 「そうなのよ。もう一ヶ月も姿を見ないのよ。どう思う?」 イアリファンが顔を ソファに深く腰掛け腕と脚を組んでいる テーブルを挟んで向かいに座っていたキールは、意見を求められて右手で顎を撫でながら答えた。 「どうって…あいつのことだ、どうせまたどっかフラフラ漂ってるんじゃないか?姿が見えないなんて日常茶飯事だろうが」 「そうなんだけど、音信不通だなんてこと、今までなかったのよ。あなたの呼び掛けにも反応がない。これは一大事よ?召喚魔が契約者の呼び掛けに応じないなんて、契約不履行で訴えられても文句は言えないわ」 論点がずれている。今は訴える訴えないの問題ではないのだ。反応がないこと自体を問題にしているのだから。 念のためにもう一度呼び掛けてみる。慎重に、出来るだけ穏やかに。 「……ダメだな、やっぱり応答なしだ」 諦めたように首を横に振った。 「故意に連絡を絶ってるのか、それとも…」 言いながら金色の瞳がちらりとキールを見る。 「連絡できない状況にあるって?あいつに限ってそんなことは…って言いたいけどな。残念ながらあの馬鹿なら十分考えられる」 深い溜め息と共に、キールは吐き捨てるように言った。 「宮殿でも騒ぎになってるの。バンなんか青筋立てて大怒りよ。草の根分けても探し出せって、捜索隊に無茶言ってるわ。見つかったらあのコ、 イアリファンが暗に言っていることは分かる。 出来れば 「刺客、ジャンの話、ヴォルの行方不明…こういうのを偶然っていうのかね?」 おもむろにタバコに火をつけて、大きくそれを吸い込む。それを横からひったくって、イアリファンが口に 「人の手が加わったら偶然とは言い難いんじゃない?とりあえず、一度宮殿に戻ってみるわ。もしかしたらふらっと帰ってきてるかもしれないし――アナタが召喚しても呼応しないんだから、期待は出来ないけどね」 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
街外れにワイチェの森というのがあり、そこは人間界にやってきた妖魔の その森の中ほどに広く開けた場所があり、小さな泉がある。そこで男達は腕試しをさせられていた。 「だあぁっ!もう、しつけーぞ、お前らッ!!」 短剣を振り回してセリオが叫ぶ。 「まったく!いい加減っ、疲れてきましたよ!!」 息を切らしながらも容赦なく目の前のモノを叩き切るのはビスファンデル。 「こら、無駄口叩く暇があったら一匹でも多くぶっ倒せよ?」 切り株に腰掛けたキールが説教をする。 「んなこと言ったってよ、お前、ハンパな数じゃねーぞ…わあっ!?」 べしゃっ。 二人に倒されて足元に転がっていた 「うわっ…ぶっ…」 覆い被さってくる透明のゲル状物体に埋もれて息が詰まる。 「あーあ…」 やれやれ、と溜め息を吐いてキールはパチンと指を鳴らした。 セリオに覆いかぶさっていた物体が音もなく消える。 「ぶはあっ!はあっ、はあっ、はあっ…くそ!死ぬかと思ったぜ…」 息も荒く、ゆっくりとセリオが起き上がる。 「ちょっと、量が、多かったですね」 セリオに手を貸すビスファンデルの息も荒い。 「でもまあ、あれだけ倒せれば、それなりの力はあるってことだ」 満足そうにキールが笑う。 「てめえ、ほんっとに容赦ねえのな…」 セリオはその場にどさりと座り込んでキールを睨みながら腕を組んだ。 それにならってビスファンデルもその場に腰を下ろした。 あれから一ヶ月、とりたてて変わったことはなかった。 いつも通りに適度に依頼を受け適度に休み、なんら変化ない毎日を過ごしていた。 だがそれは、あくまでも「キールの日常が」である。 キールを取り巻く環境には少しだけ変化があった。 セリオかビスファンデルかはたまた2人共かが、必ずといって良いほど傍にいるのだ。特に依頼を受けと ビスファンデルは貴族が故にそれなりの仕事があるのでいつもという訳にはいかないようだが、それでも暇を見つけては(あるいは無理矢理作り出しては)キールのところに顔を出すようになった。 キールが家の仕事は大丈夫なのかと訊ねると、彼は笑って答えたものだ。 「我が家には優秀な執事がいますからね。多少のことは、彼がうまく処理してくれます」 「まったく、とんだ家長もいたもんだ。そのうち当主の座を奪われるぞ」 「そうですねえ、一応、気をつけておきましょうか」 嫌味を言っても軽く受け流される始末だ。 セリオはセリオで、ヒマと言えば毎日がヒマな盗賊稼業である。 それでもギルドの若い連中をまとめる立場にあるのでどうしても抜けられない会合などはあるようだが、キールが受けた依頼のうち、セリオがいなかったことが果たして何度あったろう。 呆れたキールは友人の顔を横目で見て悪態を吐いた。 「盗賊ってのは随分とヒマなんだな?」 対する盗賊はといえば悪戯っぽく笑って翠玉色の瞳をきらめかせた。 「おうよ。治安が良くなって良いだろ?ま、もっとも、ヒマなのはオレだけだけどな」 「若頭が何ぬかす。幹部は幹部らしくちゃんと下っ端連中を束ねとけ」 「下っ端を束ねるよりお前についてった方が面白そうだもんよ。若頭の代わりはいくらでもいるさ人生は楽しむもんだって教わって育ったからな、オレは」 あのジジイ、教育方法間違ってやがる。 セリオの台詞を聞いて、キールはひそかに毒づいた。 そんなこんなで数日が過ぎていき、ある日、セリオとビスファンデルが「例の仕事」を手伝いたいと申し出てきた。 これに驚いたのはキールである。 「お前たちねえ…あれは俺の仕事なの。わかる?お前たちはお呼びでないんだよ」 何とか止めさせようとしたのだが、2人とも異様なほど頑として退かない。 仕方なく2人をワイチェの泉まで連れてきたキールは、腕試しと称してその一帯に結界を張り、周囲の妖魔に邪魔されないように空間を作った。 「これからここに大量の化け物が現れる。お前達はそいつらを倒してみろ。いいか、気を抜いたらすぐに飲み込まれちまうぞ」 そう言うとキールは手のひらを泉の水面に当て、二言三言何かを呟いた。 途端、水面がゆらりと動き、水が無数の 最初セリオとビスファンデルは呆気に取られてその物体を見ていたが、キールの声で我に返った。 「早く倒さないと飲み込まれるぜ」 一匹また一匹と這い上がってくるゲルは次第に人型を成し、こちらへ向かって歩いてくる。武器を持っているわけでも魔術を使うわけでもない、まさしく体当たりで迫ってくる。 斬っても斬っても人型は一向に減らない。それどころか、どんどん泉から這い上がってくる始末である。 とにかく2人は無我夢中でゲルを斬り続けた。 「で、俺らの腕はどうなわけ?」 「んー、どうかな。あの程度で音を上げるようじゃなぁ…」 「何言ってるんですか。私たちは優に300匹はぶった斬りましたよ。こらんなさい、この有様を」 温厚なビスファンデルが語気も荒く抗議する。 辺りを見回すと、なるほど2人が倒したゲルの残骸が足の踏み場もないほどに散らばっている。 しばらく何かを考えるように黙ってそれらを見ていたキールだが、おもむろにその破片を集め始めた。 「何やってんだよ?」 「資源を大切に、ね」 「は?」 ある程度集めると、キールは人差し指を立てて言った。 「節水にご協力を」 すると、あれだけあったゲルが一斉に ぼちゃんぼちゃんと次から次へ泉へ落ちて行きただの水に戻る。 それが終わるとなんともいえない顔でそれを見ていた2人に剣を出すように促した。 「何するんですか?」 不思議そうにビスファンデルが尋ねる。 その問いには答えずに二人の剣を受け取って、シュルンと鞘から抜いた。地面に置いた刀身に手をかざす。 ぶつぶつと何事かを呟いていたが表面上はキールにも剣にも何も起こらない。そのまま呟きが止んで元の通り剣を鞘に収めると、 「ほらよ」 と2人にそれを投げて返した。 「何をやったんだ?」 訝しげにセリオが訊ねる。 「ちょっとしたお守りさ」 魔術師は苦笑いをしてその場から立ち上がった。 「お前ら引き下がりそうにないし。一度踏み込んだら二度と踏み出せないから覚悟しとけよ」 |