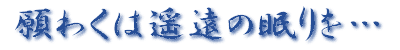
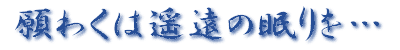
【2】 先陣は、それから二日後の深夜に来た。 魔術師には色々な類の依頼が舞い込んでくる。内容は、表は探し物、人探しなどから裏はスパイ、暗殺まで、実に多岐にわたる。 しかし歴史を辿れば、ビスファンデルに代表されるハンターが盗賊や犯罪者を狩るのに対し、魔術師は人間に害を及ぼす妖魔の類を退治するために確立してきた職業だ。 ところが才に愛された極一部の人間しかなれない魔術師に目を付けたのが金持ち連中である。しかもどういうわけか成り上がりが多い。そしてその成り上がりが大金をはたいて胡散臭い魔術師なんぞに頼ろうと言うのだ、裏の仕事が多くなるのは必然である。 この日、彼は妖魔退治に行ったのだが、思いのほか相手の数が多く、また妖魔退治が久しぶりであったこともあって、始末に手間取ってしまった。 「くそ、あの化け物、思いっきり人の腕と足を噛み切りやがって…」 無駄に力を使いすぎた上に足と腕を噛み千切られその治癒に力を使い、少々疲れて宿までの道のりを歩いていたのである。 だから、折りしも運悪くやってきた第一陣に対するキールの態度は、それはそれは冷たいものだった。 相手は3人組みだった。少なくとも、外見は人間の形だった。 「貴様の命はもらうぞ!」 「あのさ、普通、悪役の手下ってのは相手の名を確かめてから襲い掛かってくるのが王道だと思うんだけど、それは俺の思い込みか?」 やああっ、と勢いよく斬りかかって来た男を それを見て怯んだもう一人の男を面倒くさそうに一瞥すると、小さく呪文を唱えてライト・チェーンで全身のぐるぐる巻きにし、封殺した。このチェーンは時間が経つと徐々に絞まって窒息死を招く代物である。 最後の一人は同業者であった。ちょこちょこと術を仕掛けてはみたが、これと言って効果がない。体調が万全であれば指先だけで一捻り出来そうな小者だが、何よりも今のキールには昼間の労働の疲れから体力もなければやる気もない。 仕方がないので召喚魔を呼び出すことにした。 「おい」 断っておくが、召喚魔法というのは非常に難易度の高い魔術である。 基本的に妖魔というものは人間を好まない。その妖魔を使役しようということは、術者にはかなりの能力と強靭な精神力が要求される。 ということは、召喚するための呪文も自然と長くなるのである。呪文とは簡単に言えば術を発動するための準備運動のようなものだ。高度な技をやろうとすれば念入りな準備が必要だ。準備運動なしに海に入れば足が攣って溺れる。 その長い呪文を一言一句間違えずに言うだけでもかなりの訓練を要する。間違っても「おい」の一言で済むような簡単なものではない。そんな呼びかけをしても妖魔に無視されるだけである。 さて、簡潔な言葉で呼び出された召喚魔は、原型の姿で現れた。 「はあい、キール。ご機嫌いかが?あたし?あたしはとても不機嫌よ」 人語を喋ってはいるが、外見はこぶし大の白い毛玉だ。ぎょろんとした大きな目があり、鼻と口は長い毛に隠れて見えない。紐のような尻尾があり、その先端には小ぶりの毛玉が付いている。 その毛玉でキールの額をぽんぽん叩きながら抗議した。 「あのね、前から何度も言ってるんだけど、せめて名前を呼んでくれないかしら?あんなそっけない呼ばれ方じゃ、わざわざ来ようって気にもならないわ」 「あーはいはい、今度からな」 「何よその生半可な返事は。今度から今度からって一体いつからが今度からなの!?」 「今度は今度だよ。そんなことよかさ、あいつ、始末して?」 キールの指がさし示す方向に目をやって、毛玉は目をむいた。 「何よ、このあたしにあんな小者を片付けさせようって言うのっ!?ますます来た甲斐がないわ!久しぶりに呼ばれたから楽しみにしてたのにー!!」 尻尾をぐるぐる回して憤慨している。 怒るのも無理はない。見た目こそ毛玉だが、これでも立派な高位妖魔なのである。それなのに、自分から見れば赤ん坊ほどの魔力もない雑魚を相手にしなければならないとは。侮辱も甚だしいことこの上ない。 「仕方ないだろ。昼間の依頼のせいで集中力が切れてんだ。頼むよ、イア」 「もう!信じらんない!」 果たして、憐れな魔術師はイアの怒りを一身に受け、一瞬のうちのこの世を去ったようである。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
「やっぱ来たか。どんな奴らだったんだ?」 向かいの席から身を乗り出して聞いてきたのはセリオ。 「んー、黒ずくめの男が3匹。あ、1匹は同業者だったな。ちょっと手こずった」 「あなたが手こずるほどの手練れだったんですか」 ちょっと意外そうに訊ねるのはビスファンデルだ。 「別件の依頼と重なってな、疲れてたんだ。んで、イアに始末してもらった」 ナッツをつまみながらキールが答える。 ビスファンデルとセリオがグラス片手に顔を見合わせる。 「…イアに?」 「そりゃまた相手も可哀想に…」 二人は複雑な顔でしみじみと呟いた。 イアリファン。妖魔界を取り仕切る 「で、少しは動こうって気になりました?」 「どーすっかねぇ…」 掴めない表情で宙を見つめるキールから目を離し、ビスファンデルはためらいがちに口を開いた。 この台詞で、彼が確実に動くような気がした。 「ライガーの領地に侵入した盗賊が自害する前に言っていたのですが」 キールの表情は変わらない。 「『時は満ちた』、と」 ゆっくりとキールが目を閉じる。 時は満ちた。 ついに。 逸る鼓動を感じていると、傍でセリオとビスファンデルが緊張する気配がした。 目を開けて振り返ると、そこには黒いマントをかぶった男が立っていた。薄暗い店の中で、フードに隠れてその男の口元しか見えない。 その口が、微かに動いた。 (返せ。その血を、その身体を) 頭に声が響く。聞き覚えのある、背筋の凍るような冷たい声。 (返せ、その命を) 男の口元がにやりと笑い、ふっと消えた。 「…何だったのでしょうか、一体」 「さあ?」 二人の声を遠くに聞きながら、キールの頭はフル回転していた。 確実だ。 動き始めている。 あいつがまた近づいてきている。 きっともう、すぐ傍まで。 二人に気付かれないように、机の下でこぶしを握り締めた。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
「やれやれ」 盗賊ギルドの長老、ジャンポード・カフレットは深々と溜め息をついて青年を見上げた。頭は禿げ上がっているが、その代わりに豊かな白い顎鬚を蓄えている。 「55年、か。早いな」 キールがぼそっと呟く。 「一人で、やる気か?」 「当たり前だろ?これは、俺の、仕事だ」 「オレが今もお前と同じくらいの年齢なら、無理矢理にでも一緒に行くんだがな…年には勝てん」 昔のようにはいかないな、と自嘲気味に言えば、キールが苦笑いをして返す。 「身体を大事にしな、じーさん。無茶をやらかす年齢は、もうとっくに過ぎてるぜ」 前回以上に危険になる。無事でいられる保証はない。 「昔とちっとも変わらんな、キール」 つかみ所のない性格も、なんでも一人で背負い込むクセも、何もかも。 「あんたは随分と年を取ったよ、ジャン」 キールがいたずらっ子のように笑う。 もう70歳は超えているはずだ。初めて会った時は確か10代後半の若者だったから。 「ギルドの顔ぶれもだいぶ変わった」 「………」 「…少し、長く生き過ぎたかな」 急に声色が変わって、長老は弾かれたように顔を上げた。55年前と外見も中身も何一つ変わらない若者を見つめる。 そんなかつての親友の表情を見て若者は苦笑した。 「なんて顔してんだよ」 さてと、と寄りかかっていた壁から身体を離す。 「ま、吉報を届けられるように頑張りマス」 にまっと笑ってキールが部屋から出て行こうとする。ジャンポードがその背中に声をかけた。 「キール」 「あん?」 振り返った青年の前に立つと、ゆっくりと背筋を伸ばして右手を上げて眼帯の上からその左目に触れる。 前は、同じぐらいの背丈だった。彼の瞳は自分のそれと同じ高さにあった。この左目も、確かに自分の姿を映していたのに。 こんな些細なことでも過ぎた年月の多さを感じさせられる。 「無茶はするな」 黒紫色の瞳が僅かに揺れる。そして、困ったように笑った。声にはしなかったが、「無茶はどっちだよ」と言っているようだった。 代わりに出てきた言葉は。 「あの時、あんたの葬式に参列する約束したしな」 それまでは死なないように努力はするよ。 背を向けて片手を上げ、キールは扉の向こうに消えた。 「オレにはもう、黙って見てることしか出来ないんだ…」 少し震えてかすれた言葉が閉ざされた扉に吸い込まれた。 |