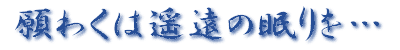
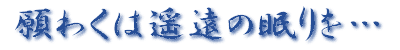
【1】 「それは…」 そう言ったきり、老人は黙り込んでしまった。 重たい空気が空間を支配する。 向かい合う青年の表情も真剣そのものだ。 「そちらにも異変が起きていると、セリオから聞きました。どうやら私だけ無関係というわけにもいかないようですね」 青年が柔らかく老人に笑いかける。 「…そんなこと、あいつは望んでおらん」 「それでも先方はご希望ですよ?」 引く意思の欠片も見つけることが出来ない口調。 ちらりと青年を見て、老人は深い溜め息を吐いた。 ◇ ◆ ◇ ◆ クラウン大陸の中央部にある国、アクバル。交通の要で、ここから大陸中に交通網が延びている。 当然貿易も盛んで、大陸中の産物がここに集まる。この国にいて買えない物はないとまで言わしめる繁栄ぶりだ。 その最北端の都市、セレスティア。古びた小さな一軒の酒場に、その男はいた。 グラスの氷が涼しげな音を立てて崩れた。 マスターから出されて2時間半、そのグラスには一度も口をつけていない。 年の頃、二十歳前後だろうか。夏の暑い盛りだというのに黒いマントを羽織り、そこから覗く服装はやはり黒の長袖と長ズボン。 透き通るような銀髪はツンツンと立っており、黒紫色の石が埋め込まれた額飾りの銀環が見える。 左目を白い眼帯で覆い、カウンターの端っこで壁を背もたれにして、黒紫色の右目で店内をぼんやりと眺めていた。 「俺をここに呼びつけたドアホはどうした?」 低い声で青年が問う。 「さて?なあに、今に来るだろう。もっとも…お前さんの顔を見たら踵を返して逃げ出してしまいそうだがね」 店のマスターが丁寧にグラスを磨きながら答えた。 「そんなことしてみろ、一瞬であの世に送ってやる。知り合いのよしみで、苦しい思いだけはさせないでやるさ。なあ、セリオ?」 いきなり声をかけられて、柱の影から青年の表情を盗み見てまさに踵を返しかけていたセリオが、びくん!と肩を震わせた。 「人をわざわざ呼び出しといて今頃のこのこやって来るとはいいご身分だよなぁ?」 話しながらも、青年はそちらを見ようとはしない。店内を眺めながら、誰に話すでもない風に淡々と言葉を紡ぐ。 「約束の時間は何時だっけな?ああ、確か11時だよな。今、何時だ?おっ、もう1時じゃないか。この店の時計はちっとばかり進み過ぎみたいだぞ、マスター」 あくまでも淡々と、話している。 その間、セリオは微動だにしない。いや、正確には「しない」のではなく「出来ない」のだ。 今、彼の首の周りには細い光が輪を作っている。むやみやたらに動けばこの輪が自分の首を締め上げるであろうことは、過去の経験からも明白であった。 その輪の作り主は、キール=トラント。2時間も待ちぼうけを食らってお冠の銀髪の青年である。 それは魔術の初歩で、多少の心得のあるものならば簡単に解くことの出来るものであるが、盗賊のセリオには生憎と管轄外であった。 「わっ、悪かったよ。お前を待たせたのは全面的にオレが悪い!頼むから、この輪っかをどうにかしてくれー!」 少しの沈黙の後、キールがことさらゆっくりとセリオの方を振り返った。 明かりに照らされた顔は意外に整っているが、何せ表情が良くない。切れ長の目はスッと細められ、百人に聞けば百人ともが近付きたくないと答えるほどの仏頂面だ。 とにかくすこぶる不機嫌なのは、誰が見ても明らかだった。 「…人を呼び出しておいて2時間も待たせた理由ってヤツをじっくりと聞かせてもらおうか、盗賊さんよ」 パチンと指を弾いて術を消してやる。 晴れて自由の身となったセリオは一つ大きく呼吸してから、緊張した面持ちで言った。 「お前を呼んだのは、オレじゃない。ギルドの長老…だ」 少し言葉に詰まったセリオをじっと見つめ、キールは薄く笑った。 「へぇ?」 セリオが歩き出し、その後を無言でついて行く。 キールは、心の奥で燻ぶる小さな何かを押し殺した。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 「盗賊とハンターの密会が拝めるとは、世も末だな」 その光景を見て開口一番、キールはそう吐き捨てた。 「お待ちしていましたよ、キール」 嫌味も意に介さず柔らかな笑顔で彼を迎え入れたのはビスファンデル=ライガー。セレスティア有数の貴族・ライガー家の当主である。 意外な人物の登場に小さく舌打ちをして眉を顰めた。 「俺の記憶じゃお前はハンターだったと思うんだが、ミイラ取りがミイラになったか?」 ハンターとは盗賊を狩る職業である。賞金首の盗賊が主な獲物だ。 その、本来は敵同士である盗賊とハンターが仲良く密談しているとは。 「私はハンターとしてここにいるわけじゃないんですよ。ライガー家の当主として、こちらにお邪魔しているんです」 「なんだ、家に侵入でもされたのか」 「――ええ、大きなネズミが一匹、入り込みました。…とても大きな、ね」 何か含むところのあるビスファンデルの言い草が、キールの眉間にシワを作る。 黒紫色の瞳がハンターから離れ、代わりにその正面に座っている老人を捕らえた。 俯き加減の老人がその視線に気づいたのか、顔を上げないまま低く問う。 「なんだね」 「それはこっちの台詞だ」 「断っておくが、止めろとは言ったぞ。だがお前のご友人は年寄りの言うことなど聞いてはくれん」 「能書きはいい。俺をここに呼んだ、その用件は?」 「…災いが来た。ギルドと、ライガー家と、それからセリオにも」 ここで初めて老人が顔を上げた。若い頃の精悍さの面影が残った顔つきだ。 「近々だ。警戒せざるを得ない。いずれ、お前のところにも来るだろう」 「…へえ、そいつぁ大変だな」 キールは低く笑った。体の奥で何かが動いたような気がした。 「どんな災いか知らないが、せいぜい頑張ってくれ」 「高みの見物でもするおつもりですか」 「冗談。金をもらっても見物はごめんだ」 「事は重大だぞ」 「だからだろ?」 押し問答はしばらく続いた。 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ そこは石造りの地下室で、部屋の中には椅子が一つ、机が一つだけあった。 机の上には明かりのロウソクと、やりかけのチェス盤。 男は椅子にゆったりと腰をかけ、脚を組んで部下の報告を聞いていた。 「どうやらあの男に接触したようです」 若い女の声だった。 「ふん。これであいつは動き出すかな?」 低くくぐもった男の声が言う。 「それが、話は平行線のままのようです。意外に慎重ですね」 「昔っからそうだよ。人間でも物事でも、あいつはまず疑ってかかる。警戒心の塊みたいなやつだからね。まるで野生動物さ」 何を思い出したのか、男は喉の奥で笑った。 「とりあえず、部下を何人か向かわせました。それでおそらく動き始めるものと思うのですが」 その言葉に男は楽しげな笑みを浮かべる。小首を傾げて呟いた。 「どうかなぁ。彼は面倒臭がりだからね。まあ、部下たちにも火付け役程度の働きぐらいはしてくれることを期待しようか」 「…では、失礼致します」 一礼して、女はその場から立ち去った。 ロウソクの炎が揺れて、男の顔をゆらゆらと照らす。顔は笑っているものの、その目は獲物を前にした肉食獣のように輝いていた。 「変わってなさそうで嬉しいよ、キール。もうすぐだ。もう少しで会える」 机上のチェス盤では、黒のキングがチェックメイトされた。 |